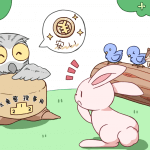お金を貸したり、返済する時に贈与税がかかる場合があるって本当?贈与税がかからない条件は?
今回の記事では、贈与税の種類や、贈与税が発生しないケースについて、詳しく見ていこう。
まずは、贈与税と相続税の違いについて解説するよ。
「贈与税」とは、金銭や不動産などを対価なしに受領した場合に「もらった側の人」にかかる税金です。
しかし、状況によっては、お金を貸し借りしただけなのに「贈与した」とみなされて課税されてしまうことがあります。
あげた、もらったつもりもないのに贈与税を課せられるのは不本意と感じる人が多いのではないでしょうか。
本記事では
- 「贈与税とは何か、贈与税の課税方法と特徴」
- 「贈与のつもりがないのに贈与とみなされてしまうのはどのような場合か」
- 「贈与税の軽減や非課税の特例とは」
といった点を解説します。
贈与税と相続税の違い
まず前提として、贈与税と相続税の違いを確認しておきましょう。
贈与税と相続税は混同されがちですがまったく別のものです。
贈与税は、親族間でも他人間でも、生きている譲渡人が無償で金銭や不動産等の財産を譲り渡した際に「譲受人に」かかる税金です。
一方で相続税は(他人への遺贈など例外はあるものの)基本的には被相続人(亡くなった人)から相続した財産につき「相続人に」かかる税金です。
贈与税や相続税については制度が細かい上に減税、免税の措置も多く、毎年何らかの改正が入ることもありなかなか一般の人が全貌を把握することは困難です。
あらかじめ最も基本になる知識をつけた上で、
- 「どのようなケースで税が課せられるのか」
- 「節税のためにしておける措置はあるのか」
といった点については、税理士に相談して慎重に判断することが大切です。
では本記事の中心となる贈与税について、概要を確認していきましょう。
贈与税とは
冒頭に説明したとおり、「贈与税」とは、(法人ではない)個人が無償で金銭や不動産などを譲渡したことに対し、譲受人に課される税金です。
贈与税には「暦年課税」「相続時精算課税」の二種類がありますが、これらについては下記に解説します。
贈与税の計算方法
贈与税の具体的な計算式は、暦年課税(下記に解説)を使う人の場合は
「贈与を受けた金額ー110万円(1年間に贈与税がかからない限度、基礎控除とよばれる額)×税率ー控除額」
ということになりますが、ややこしいのは「贈与を受ける金額、そして、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の関係によって税率が変わってくる」ということです。
贈与税の種類
手続きを行わなければ、暦年課税が適用されるよ。
いったん、相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れないから注意しよう。
上記に触れたとおり、現在、日本の贈与税には「暦年課税」「相続時精算課税」の二種類の課税方法があります。
原則として特に何も税務署に届出を行わなければ「暦年課税」が適用され、届出を行った人のみ「相続時精算課税」が適用されます。
二種類の比較をまとめると次のとおりです。
|
暦年課税 |
相続時精算課税 |
|
|
非課税枠 |
年間110万円まで |
年間110万円まで 累計2,500万円まで |
|
税率 |
10%~55% |
2,500万円まで非課税 2,500万円を超える部分につき20% |
|
贈与者と受贈者の条件 |
なし |
贈与年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与 |
|
贈与回数の制限 |
なし |
非課税枠に達するまで何回でも可 |
|
申告等の手続き |
年間110万円を超えたら翌年確定申告 |
相続時精算課税を選択する贈与を受けた翌年に税務署に選択届を提出、以降は贈与を受けた翌年に確定申告 |
|
相続税との関係 |
相続開始から遡って7年以内に行われた生前贈与財産は贈与時の価格を相続財産に加算 |
相続時精算課税を用いて行われた贈与財産は、贈与時の価格で相続財産に加算 |
|
注意点 |
相続時精算課税への変更はいつでも可能 |
相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻ることができない |
では、二種類の贈与税の制度について少し詳しく見てみましょう。
暦年課税
「暦年課税」が適用される人の場合、受贈者につき年間110万円(基礎控除)の範囲に収まる贈与であれば課税されず、申告義務もありません。
なお、年間110万円を超える贈与に関しては申告義務が生じますが、上記のとおり税率は
- 「誰から誰への贈与なのか」
- 「いくら贈与したのか」
に応じて割合が決まっています。
詳しくは以下を参照してください。
参照:※国税庁タックスアンサーNo.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
相続税の申告は「受贈者」が「受贈者の住所地を管轄する税務署に」、「贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに」行い、納付も上記期間に済ませなくてはなりません。
相続時精算課税
暦年課税の他に、税務署に届け出ることにより選択できる制度として「相続時精算課税」があります。
相続時精算課税の概要は次のとおりです。
- 「2,500万円までの贈与につき非課税(数回に分けての贈与でもOK)」
- 「2,500万円を超える贈与については一律贈与額の20%の税率で贈与税を課税」
- 「相続時精算課税を用いて贈与した額については、贈与者が死亡し相続が発生した際に『相続財産』の中に参入する(=持ち戻す)」
相続時精算課税を用いることにより恩恵を受けることができる代表的なケースは次のようなものがあります。
【ケース1】
「贈与者の死亡時に存在する贈与者(=死亡した人)名義の財産+相続財産相続時精算課税を用いて生前贈与した額」≦「相続税の基礎控除額」
上記にあてはまる人、言い換えると「相続時精算課税の分を持ち戻してもなお、相続財産が基礎控除の範囲に収まっているため申告義務がない人」ということになります。
※相続税の基礎控除・・「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」
逆に、相続税申告をしなければならなくなりそうな状況が確実に予想される人は相続時精算課税を使うことにあまり税務的なメリットがないといえます。
【ケース2】
「将来大幅な値上がりが予想される財産を相続時精算課税を用いて贈与する」
ケースでも節税効果があるといえます。
例えば成長、値上がりが予測される企業の株式などがこれにあたります。
相続時精算課税を用いて贈与した財産は、仮に相続財産に持ち戻したとしても「贈与時」の基準で評価、計算されるため、相続時価額ー贈与時価額の差額分を圧縮できることになります。
なお、相続時精算課税の注意点として特に大切なのは次の項目です。
- 相続時精算課税を選択する最初の贈与の翌年に税務署に「相続時精算課税選択届」を出さなければ通常の贈与税が課税されてしまうので、忘れないように注意する必要がある。
- いったん相続時精算課税を選択してしまうと暦年課税には戻れない。
将来の相続財産の予想額を考慮した上で適切な方法を選択する、また税務署への選択届を確実に行う必要があることからも、最初から税理士に相談、依頼する方が無難です。
みなし贈与と判断されるケース
自分では贈与したつもりではないのに税務署から見て「実質的には贈与にあたる」と判断し課税されてしまう行為がありますが、これを「みなし贈与」といいます。
贈与のつもりではなかったので贈与税申告を行っていなかったケースですと、延滞税(最大年14.6%)や加算税(15%から40%)がかかってくることがあるため、通常の申告より重い負担となります。
典型的なみなし贈与の事例を挙げておきますので、下記のようなケースで申告漏れがないように注意しなければなりません。
- 財産を有償譲渡したものの、市場価格として適正な価格よりも著しく低い対価であると判断されるもの。
例えば不動産であれば過去の裁判例より「時価の80%未満の場合には税務署からみなし贈与と認定される可能性が高い」といえます。 - 債権者から借入の返済を対価なしに免除された場合。
- (特に親族間の貸し借りなどにみられる)お金を借りたが、返済に関する決まり事がきちんと行われておらず、催促もされないような場合。
みなし贈与を回避するためには金銭消費貸借契約書をしっかりと作成する、返済を契約通りに行うなどの対策が必要となりますが、やはり税理士に相談して間違いのない内容にすることが大切です。
贈与税について減税や免税の特例
贈与税については、一定の要件にあてはまるケースで減税、免税の措置が設けられています。
贈与税の税率は国税でも最高レベルに高いため、教育資金や住宅資金の贈与、夫婦間贈与など配慮が必要な場面では大幅に減税となることがあるのです。
では、それらの例を見てみましょう。
生活費・教育費
上記「暦年課税」で「1人年間110万円を超える贈与」については贈与税が課税されると解説しました。
ただし例外として、扶養義務者(親など)から扶養される者(子など)への通常の生活費に該当するものには110万円を超えていても課税されません。
例えば、学費、文房具、教材費などが非課税にあたるものの例です。
また、教育費の贈与については、直系尊属(祖父母等)から30歳未満の者への教育資金を一括で贈与した場合に「1,500万円までは贈与税非課税とする」特例が設けられています。
この「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度」を適用できる要件の主なものは次のとおりです。
- 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた「教育資金」に充てるための贈与であること。
※期間は今後延長される可能性もあります。 - 直系尊属から30歳未満の者への贈与であること。
- 金融機関との一定の契約に基づいて行い、金融機関の営業所等に教育資金非課税申告書を提出すること。
- 教育資金として支出した金額について金融機関等に領収書を提出すること。
- 金融機関との教育資金口座にかかる契約が終了した場合、教育資金として支出されたと認められた金額を控除した額(=残余の金額)を税務署で贈与として申告します。
教育資金にあたるのはどのような場合かなど、上記以外にも詳細なルールがあるため、この制度を利用する人は税務署から発行されているリーフレットを参照することをおすすめします。
参照:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
夫婦間での贈与
20年以上連れ添った夫婦の間で「居住用不動産」の贈与を行う場合、2,000万円+暦年課税の110万円=2,110万円までは贈与税がかからない「おしどり贈与」とよばれる制度があります。
おしどり贈与を適用できる要件は以下のとおりです。
- 婚姻期間(法律婚のみ)が20年以上の夫婦間の贈与であること。
- 居住用不動産の贈与もしくは居住用不動産取得のための金銭の贈与であること(借地権も含む)。
- 現に居住しており、住み続ける見込みであること。
※贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
資産が夫に偏っている場合などは、夫から妻に不動産の名義を移すことにより夫が死亡した際の相続税対策になることもあります。
また、夫に前妻との間の子供がいる場合に、後妻を相続紛争に巻き込まず居住する家を確実に確保しておきたいなど心理的な安心感を得る効果もあります。
ただし、おしどり贈与を利用するにあたっては注意点もあります。
- 贈与による不動産の名義変更をする際、相続よりも登録免許税の税率が高くなる。
つまり不動産の固定資産税評価額によっては税負担や司法書士報酬などの移転コストが予想外にかさむため、それらを計算した上で利用を検討するべき。 - おしどり贈与によって無理に生前贈与しなくても、相続の際に使える税軽減の特例である「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を利用すれば大幅に減税あるいは免税となることも考えられる。
よって、相続の場面まで予測して考えるべき。
具体的に名義変更にいくらコストがかかるのか、あえて相続ではなくおしどり贈与を使うメリットとデメリットを比較検討し、慎重に決定することが望ましいといえます。
住宅取得等資金
祖父母や親などの直系尊属から子や孫に住宅購入、リフォームの資金として贈与が行われた場合、非課税限度額(下記)までは贈与税が非課税となります。
非課税を適用するための要件の主なものは次のとおりです。
- 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与であること。
※期間は今後延長される可能性もあります。 - 非課税限度額については、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円とする。
- 受贈者は贈与者の直系卑属であること。
- 贈与を受けた年の1月1日において受贈者が18歳以上であること。
- 受贈者が贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 平成21年から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与の特例」の適用を受けたことがないこと。
- 自己の配偶者、親族など一定の関係者からの住宅取得ではないこと、またはこれらの人との請負契約等による新築または増改築をしたものではないこと。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実と見込まれること。
この特例については「新築、取得、増改築」に関する要件なども細かく定められていますので、利用する人は税務署から発行されているリーフレットを参照することをおすすめします。
参照:「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等のあらまし」
子どもの結婚や子育ての資金
結婚、子育て資金の贈与については、直系尊属(祖父母等)から18歳以上50歳未満の者への資金を一括で贈与した場合に「1,000万円までは贈与税非課税とする」特例が設けられています。
この「父母などから結婚、子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度」を適用できる要件の主なものは次のとおりです。
- 平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に行われた「結婚、子育て資金」に充てるための贈与であること。※期間は今後延長される可能性もあります。
- 直系尊属から18歳以上50歳未満の者への贈与であること。
- 金融機関との一定の契約に基づいて行い、金融機関の営業所等に結婚、子育て資金非課税申告書を提出すること。
- 結婚、子育て資金として支出した金額について金融機関等に領収書を提出すること。
- 金融機関との結婚、子育て資金口座にかかる契約が終了した場合、結婚、子育て資金として支出されたと認められた金額を控除した額(=残余の金額)を税務署で贈与として申告します。
結婚、子育て資金にあたるのはどのような場合かなど、上記以外にも詳細なルールがあるため、この制度を利用する人は税務署から発行されているリーフレットを参照することをおすすめします。
参照:「父母などから結婚、子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
障害者への贈与
障害を持つ人については障害の程度に応じて贈与税が軽減される制度が定められています。
前提として、障害者の定義について「国税庁タックスアンサー」には次のとおり記載されています。
障害者とは
障害者とは、次に掲げるような心身に障害のある方です。
〈ロ〉精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方(重度の知的障害者と判定された方は特別障害者となります。)
〈ハ〉精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障害等級が1級と記載されている方は特別障害者となります。)
〈ニ〉身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方(障害の程度が1級又は2級と記載されている方は特別障害者となります。)
〈ホ〉戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は特別障害者となります。)
〈ヘ〉原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者となります。)
〈ト〉いつも就床していて、複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者となります。)
〈チ〉精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方に準ずるものとして市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている方(〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方のうち特別障害者となる方に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方は特別障害者となります。)
障害者の贈与税については、次のとおり非課税の規定が設けられています。
- 特別障害者以外についての規定
「精神に障害がある方については、信託受益権の価額のうち3,000万円まで→非課税」 - 特別障害者についての規定
「特別障害者については信託受益権の価額のうち6,000万円まで→非課税」
信託とは、自分(委託者)の財産をあらかじめ定めた目的に従い、信頼できる他人(受託者)に管理してもらう制度です。
信託受益権とは、信託財産を使って得られた利益を還元してもらう権利であり、この権利を受ける人を「受益者」といいます。
障害者については信託を利用することで親など親族の死亡した後でも信託銀行等に財産管理を任せられるというメリットがあります。
まとめ
- 贈与税は財産を無償で譲渡された際に「受贈者」が申告、納税する義務を有する。
- 贈与税の課税方法としては「暦年課税」「相続時精算課税」の二種類があるが、いったん相続時精算課税を選択し税務署に届け出ると暦年課税に戻ることはできないため注意が必要である。
- 贈与税にはさまざまな減税、非課税制度があるため税理士に相談しながら適用を検討するべきである。
西岡容子
青山学院大学卒。認定司法書士。
大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。
平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。
「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。
以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。
債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。
■略歴
昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる
平成5年 青山学院大学卒業
平成14年 司法書士試験合格
平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務
平成18年 司法書士西岡合同事務所開設
■登録番号
司法書士登録番号 第470615号
簡易裁判所代理権認定番号 第529087
■所属司法書士会
熊本県司法書士会所属
■注力分野
債務整理
不動産登記
相続
■ご覧のみなさまへのメッセージ
通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。
債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。
借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。
なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。
法律家に「言われるがまま」ではなく、自分の意思で、納得して手続きに入るためにも当サイトで正しい知識をつけていただけたら幸いです。
最新記事 by 西岡容子 (全て見る)
- 成人年齢が引き下げられましたが、10代でも債務整理はできますか?注意点は? - 2026年2月18日
- 物価が高くなっていますが、生活費の中で返済額の割合がどれくらいになったら債務整理を考えたほうがいいですか? - 2026年1月15日
- 遺品を売却した際に得たお金はどのような扱いになりますか?相続税などの税金に影響はありますか? - 2025年12月17日
厳選!おすすめ記事BEST3
-
1
-
債務整理のベストな選択とは?経験談を踏まえて基礎情報から弁護士の選び方まで一挙解説
もし多額の借金を抱えてしまった場合、もしくは借金を返せなくなったと思った場合、誰 ...
-
2
-
債務整理に注力しているおすすめの事務所一覧【徹底調査】
当サイトでは、実際の取材や債務整理の相談を行なった体験談をもとに、おすすめの弁護 ...
-
3
-
債務整理のベストな選択とは?経験談を踏まえて基礎情報から弁護士の選び方まで一挙解説
もし多額の借金を抱えてしまった場合、もしくは借金を返せなくなったと思った場合、誰 ...
-
4
-
任意整理の弁護士費用はどれくらい異なるの?おすすめ事務所を徹底比較
借金に関する相談は、弁護士事務所や司法書士事務所において無料で行なうことができま ...
-
5
-
債務整理のベストな選択とは?経験談を踏まえて基礎情報から弁護士の選び方まで一挙解説
もし多額の借金を抱えてしまった場合、もしくは借金を返せなくなったと思った場合、誰 ...
-
6
-
ひばり法律事務所の評判・口コミを徹底分析 直接取材でわかった依頼するメリット・デメリット
ひばり法律事務所の特長 累計1万件の債務整理対応実績 緊急性に応じて即レスするス ...